放送技術"1980年2月号掲載
第2回海外音響技術視察・アメリカ編
アメリカのホール、音響技術に学ぶ(抜粋)
出席者:栗原 信義(NHK)
福井泰一郎(松下電器)
八板賢二郎(国立劇場)
八木 堯敏(第一音響設備設計)
司 会:及川 公生
日本音響家協会(若林駿介会長)と日本音響コンサルタント協会(永田穂会長)の共催による、第2回海外音響技術視察・アメリカ編が、1979年9月に実施された。ロサンゼルスのハリウッドボウル、ミュージックセンターの音響技術をはじめ、ラスベガスではステージショーを、またスピーカのアルテック社と調整卓のクワドエイト社の工場見学を通して、アメリカの音響技術に対する設計思想を学ぶなど、意義深い視察旅行であった。
ここでは、この視察旅行を通じて、アメリカの音響技術が日本の音響技術者の目にどう映ったか、参加者にご意見を伺った。
アメリカに学ぶもの
──司会の及川です。皆さんアメリカの音響技術を視察に行かれて、それぞれの立場で自分の仕事に関連の深いものが印象に残っていると思いますが、それ以外にも学ぶものがあったのではないでしょうか。最初に参加の目的から話を進めていきたいと思います。まず、ハードとソフトの接点におられる松下電器の福井さんから伺いましょうか。
福井:初めて海外に出たので何もかも新しく感じました。私は四つの目的をもって行ったんです。一つはアルテックのスピーカの設計思想で、ハード面の考え方と生産工場のあり方です。それにクワドエイトでは工場における生産工程とホール、レコーディング会社に対する納入実態です。第三は、アメリカのホール、スタジオおよび屋外音響システムを見学すること。これが今回のメインだったわけです。もう一つは、新しいホールやスタジオシステムを考える場合に、メーカーとして設計施工、あるいは施工に対しての立場とか連係プレイがどうなっているか、こういったことを見たいということで参加したわけです。
──八木さんはハードが主だと思いますが、その他にホールを見たり、音楽を聞いたり、ソフトも含めて仕事に関すること以外にも幅広い見学をされたと思いますが、どうでしょうか。
八木:私は78年のヨーロッパに引き続いて参加したわけですが、今回はメーカー見学があるというので、主にクワドエイトのハード的なやり方と設計思想がどうなっているか、ということと、実際のホールなり劇場で機器の運用がどうなっているかを見たかったわけです。それとホール音響のシステム設計が私共の主な仕事なので、全体のシステム設計をどうやっているのか、たまたまハリウッドボウルとディズニーランドという屋外の音響視察が組込まれていたので、そこで実際にどんな音を出しているか興味があったわけです。
──印刷物や聞いた話より、自分の目と耳で確かめられますからね。次はNHKのホールを中心に、番組などでミクサ一として活躍されている栗原さん。
栗原:今回の最大の目的は外国へ行ってみたいということで、たまたまこのツアーがあったので参加したというのが本音です。個人的にアメリカってどんな所かということを、仕事と趣味の分野をとおして理解できればということで參加したわけです。ハード的なもので何が見たいとかいうより、ソフトというか仕事を、どういう発想、どういうやり方で、どういう結果を出しているかが興味のあるところで、そういうことを通してアメリカの人とか土地といったものを理解できれば、という目的で行ったわけです。
──同じように国立劇場でホール音響に携わっていらっしゃる八板さんはどうだったですか。
八板:私の場合は、音響機器や設備のことではなく、音響設備がどのように活用されているか、どういう思想で音響デザインをしているのかを学ぼうとしました。
メーカーの見学では、日本のメ一力一と違って、どういう思想で作っているのかを確認したかったわけです。アメリカの音響事情に関して、意外とうわべだけの情報が多いので、自分の目と耳で確かめたいという気持で参りました。
アメリカ音響技術の設計思想
──栗原さんが、漠然とアメリカという土地を見たいと言われましたが、私の海外旅行の経験からもひしひしと感じたことで、大賛成ですね。日本以外の空気に触れるとか、違う人種に会うということは、即仕事には関係ないわけですが、違った環境にいると、何かで自分の仕事に関わることが出てきますね。ザックバランに栗原さん、初めての海外旅行での第一印象はどうだったですか。
栗原:成田を飛び立ってサンフランシスコの陸地を見たときは、大きくて変っているなという印象を受けたのですが、内陸に行くと人家が密集していて、日本と変わらんわいとまず一安心したんです。市内見学では、たしかに異国の地であることの実感を深く持ったのと、いままでにも写真とか紀行文を見ているので、まったく知らない世界ではないんですが、自分の目で見て聞くのとでは、百聞は一見にしかず、の実感ですね。
──空気が乾燥しているというのが私の第一印象だったのですが、なるほどこれならば音がいいはずだと思ったことがあります。八板さんどうですか。
八板:気候や璟境によって、そこに生まれてくる音楽というものは全然違ってくるはずですね。だから、この乾燥したアメリカ西部の気候がウェス卜コーストサウンドを創り上げているのだなあと、身にしみて感じました。音響機器メーカーも、演奏家も、ミクサ一も、すべて気候に支配されていると言っていいのではないでしょうか。
福井:何事についてもビッグだという感じです。ハリウッドボウルでは客席のド真中に調整卓を持ち込んでいるし、ホールも予裕をもって作ってある。それと、空気が乾燥しているので、雨や湿気を気にしないで設計、設置ができるのもうらやましいですね.
──八木さん、アメリカ人気質の中に、八木さんの所でやっておられる設計思想と違っているところはありますか。
八木:ミュージックセンターの卓も、ハリウッドの新しい卓も見ましたけれど、たしかに違った思想はありますね。自分の所に必要なだけの機能を持った設備を入れている。ただ、ユニットのような単体的なものはやはりアメリカの方が内容的に良いものがあるけれど、システム全体ということでは日本の設備も進んでいるのではないでしょうか。それから、ミュージックホールなどを見て感じたのは、アメリカのホールは何でも多目的ではなくて、限られた多目的ではなかろうかということです。設備そのものの考え方は日本の方がグレードは高いというか、アメリカはシンブルで機能本位に作られているような印象を受けました。
多目的ホールと無目的ホール
栗原:まさにそのとおりだと思います。基本的な部分でホールや劇場の音響に対する金の掛け方がベラボ一に違うんですね。それがどこから来るのか知りたかったのですが、ついに知り得なかったのが残念です。一つ考えられるのは、娯楽設備とか遊びに対する価値観が非常に高いということです。映画の迫力を何倍にもしてくれる音響に対する認識がまず日本と根本的に違いますね。日本は音が出ていればいいという発想がどこかにあるのではないでしょうか。お金を掛けたいい設備で、安く楽しめる。そこに日本とアメリカの本質的な差があるように感じます。
──私たちが催し物のプランを立てるときに、照明とか舞台設備はすごい予算があるのに、PAは鳴っていればいいくらいのところで、結局、音は最後になってしまう。楽しみに対する価値観がぜんぜん違うということをひしひしと感じますね。
八板:日本の劇場において音響というセクションの位置付けが全体に立遅れているかも知れませんが、これはやはり舞台の電気音響の歴史が浅いからではないでしょうか。今から10年前までは、舞台音響といえば芝居の効果音が主な仕事でしたし、歌謡ショーでも歌マイク以外はほとんど使わずにやっていましたからね。しかし、今では主要劇場やホールでは、音響の予算も多く取れるようになったし、一応、音響の重要性というものが徐々にですが認められてきているようですね。ただ、電気音響よりも建築設計、建築音響の進展がみられません。もっと思いきったことをやってほしいものです。
栗原:日本の劇場も音響設備だけをみるとかなり良いのではないでしょうか。でもドロシー・チャンドラ・パビリオンではロビーと場内との仕切りの2重ドアが10メートルくらい離れていますね。その間は部厚いジュータンの通路になっていて、日本ではとても考えられない設計です。部厚い1枚のドアで音を遮断するのではなくてスペースをとっておけばいいという、すべてがゆったりとできていますね。
八板:日本のホールの設備はいろいろと揃っているが、実際に運用するにはちょっと足りないとか、使用しないで遊んでいる設備が多いですね。アメリカなどでは目的に応じて必要なものを揃えているから、無駄な装置はないようですよ。
──福井さん、日本のような多目的ホールのシステムを組み上げるには相当苦労があるでしょう。
福井:多目的は無目的だということをよく聞きます。欲張って計画しても多目的な用途の全部をクリアできませんから、それぞれが妥協してしまうわけです。そのために逆に中途半端になって使いにくいものになる。先程ビッグだと言いましたが、ミュージックセンターにはクラシックホールと小劇場、これは気楽に集える開放形ですね。もう一つはモダンタイプと、この三つのホールがありますが、日本ですとこれを二つくらいに分けられ、それも容量の違いくらいで設備はほとんど同じ内容です。アメリカははっきりと分けていると思うのです。多目的にしても用途をわきまえているのではないでしょうか。
ラスベガスのショーを見て
──多目的の用途をわきまえているというのはいいことですね。
話を変えて、ラスベガスでショーを見たそうですが、そういうショーと関係の深い番組を手がけていらっしゃる栗原さん、何か違いを感じられましたか。
栗原:上演されている内容のクオリティがまず違います。幕間を埋めるコメディアンの5分から10分のショーだけでも十分に楽しめてしまう。そういうショーは音響が楽ではないでしょうか。日本の場合、出演者の声量を補足したり特殊効果を加えて、聞かせるために膨大なPA設備が必要になったりと、その差を非常に大きく感じました。
八木:音響設備を見学できなくて、ショーを見学したわけですが、浅草のSKDを一回り大きくしたような感じのショーでしたね。芸の質が良いのか、言葉は分らなくても引込まれてしまう。場面転換も暗転のテンポが速くて、最後になってから音響はどうだったかな、と思ったくらい迫力がありましたね。

▲ラスベガス
八板:ショーは出演者とスタッフとのアンサンブルが問題ですから、そこで音響だけをどうのこうのということは基本的にはおかしいことですが、音響の私たちにも音を気付かせないほどショーアップされていましたね。
──日本では、さあこの音を聞いてくれという音響の出しゃばりがあるんですが、演出が上手だと音響は不要という感じになりますね。
栗原:途中、何度か音響ツアーなのだから音響を見なければと自分に言い聞かせてプロセニアムスピーカを見ると、必要な所に必要な音量を必要な質で上手に出している。しかもテープ(録音)のサウンドで十分と割切っているのか、ほとんどテープですね。それに生の音を足して舞台の進行と合わせている。生でなければタイミングが合わないところは生でやっている。合理的というか、そこのセンスが非常にいいですね。
八板:そのテープも、日本ではスタジオの中で録音したような音を録りますが、MGMで聞いた音は生の演奏をPAしているかのような音でした。最近も経験したんですが、ある役者が出演できなくなったので、お詫びのあいさつを旅先の楽屋で録って送ってきたものを、劇場で再生したんです。そうしたら満場の拍手が来るほど臨場感があるわけです。非常に悪い状態の録音でしたが、それがかえって臨場感を出したわけで、舞台の袖であいさつしているようでした。こういう演出も必要なんですね。テ一プ音から生へ、生からテープ再生へというすり替えが非常にうまいし、臨場感を出すために計算された音づくりをしているように思えるのです。
──アメリカ人気質というか、割り切るところは割り切って、神経を使うところは計算尽くなんです。
栗原:PAに限らず、アメリカはプロ意識が強いですね。どんな企業の人も、自分はこれで飯を食べているんだと、お金をもらっている以上に、仕事に誇りを持って、他の人に負けない気概があって、技術、知識の平均レベルが高いような気がします。
八板:そういう音響に対する主張がないとプロとしてやっていけないほど、生存競争のはげしいお国柄だと思いますね。
──ミクサ一には職人気質というようなものがありますが、福井さん、ハードの方はどうですか。
福井:アメリカはセクショナリズムなんですね。そのかわり自分の仕事はパーフェクトにやる。そのへんが日本とかなり違います。
──若林駿介さん(協会会長)がアメリカで仕事をされたとき、マイクを動かすのに花瓶がじゃまになったので端に移したところ、花瓶を扱う係がいるということでえらく怒られたそうです。職人気質というのは日本人のほうがあるような気がしているのですが、セクショナリズムが発達しているのでしょうね。
それからハリウッドボウルに行かれたそうですが、八板さん、ああいう屋外コンサートホールをご覧になって、どうですか。
八板:あのようなスペースで常に新しい音響の技術開発ができるといいですね。メインスピーカの構成とステージ天井、それにサイドステージに付けられた反響用の円筒形の柱にはたいへん興味を持ちました。それと、公演中は上空を飛行機が飛んではいけないという条例があるんですね。
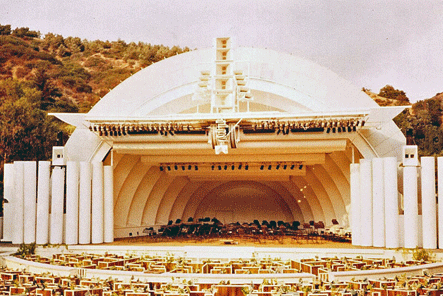
▲ハリウッドボール
──娯楽に対する投資というか、飛行機の航路まで替えてしまうわけですか。
八板:そういう環境の中で仕事ができるということはうらやましい限りです。
栗原:あの劇場で感じたのはそれですよ。たかが遊びじゃないかと、日本ではきっと重要な目的で飛行機は飛ばしているんだからと言うかも知れませんがね。公演中はサーチライトで表示して、それが見えたらその上を飛んではいけないと、そういう意識が自然に行渡っていることはすばらしいことで、日本は機械の物まねだけでなく、そういうことも輪入してほしいと思いましたね。
──そういう思想は大いに真似たいですね。バーバンクは如何でしたか。
バーバンクの映画の音創り
八板:映画の録音については良く知らなかったのですが、野外のロケではワイヤレスを使って、屋内では逆にガンマイクを使っていたのです。それと、劇場では有線マイクを使って、ワイヤレスはあまり使わないのですね。そのへんが日本と違っているようです。やり直しのきかないものにはトラブルの少ない方法を用いるということでしょうか。やり直しのきく映画撮影のときは、ワイヤレスマイクを付けて、オンマイクで同時録音してしまうのです。録音技術者に「電波が途切れたらどうしますか」と質問してみました。その答えは「取り直します」でした。
栗原:映画の音付けをするダビングスタジオが映画館のような大きな空間とスクリーンを使っている。そこに映写して最上席に当たる部分に10メートルくらいのミクシングマシンを備え付けて4~5人のエンジニアがやっているわけです。実際の映画館の何分の1というようなケチなことをしないで、同じ容積と同じ状態の所でミクシングバランスを作るんですね。それと、マルチのPCMレコーダを使っていたのですが、ミクサ一の間では非常に評判がいいと言うことです。伝統を重んじる映画界ですが、いいものは積極的に使っていこうという姿勢が見受けられましたね。
音は大切にされています。それにも拘わらず日本で上映される音の悪さは、声を大にして言っておきたいですね。娯楽設備への投資がケタ違いです。
ドロシー・チャンドラ・パビリンにて
──ロサンゼルスのドロシー・チャンドラ・パビリンについては、ここで録音されたレコードもたくさん出ているしロビーのすばらしさはたいしたもので、私も強い印象を持っております。日本の無目的多目的ホールではとても味わえない心の和むホールですね。
八板:われわれのセリフの収音とは全く違うことをやっていました。直接音を収音するのではなく、床で反射した音を拾っているのです。その方式によると音源の遠近の差があまりないし、ハウリングマージンもかせげるので、劇場としてはありがたい話です。日本でも取り入れてもいいんじゃないかと思いました。
──ホールのミクサ一にとっては興味のある話ですね。マイクはどんなセッティングですか。
八板:舞台端に2 メートルぐらいの間隔で仕込むのですが、普通ですと出演者の顔のあたりを狙って仕込みますが、これは床から5センチくらいの高さから床の方に向けて仕込むのです。(この手法は後にバウンダリーマイクとなりました)
──マイクの先端を床の方に向けているんですか。
八板:そうすることで、演者の声が床で反射した音と直接音の両方が同時に入って来るわけです。直接音だけを拾わないということは、マイクに近づいたときとオフになったときに音の差があまり感じられないわけです。それに、俳優の豊かな音声には驚きました。電気音響より生の音がよく聞えましたね。あれだけパワーがあると収音も楽です。
また、出演者自身も音響のことを把握して意識してやっているように見受けました。ですからエンジニアも非常に楽だし、それで音がまとまってしまうのですね。もともと俳優もいいし、音楽もいいのだから音のバランスをとるということより、ホールの音場補正をすればよいわけです
──栗原さんも何か刺激があったんじゃないですか。
栗原:客席にステージ方向の縦の通路がないですね。
八木:あれで非常時には満席であっても1分30秒以内に全員退避できるということでした。
──それはヨーロッパ方式なんだそうです。ヨーロッパのホールはほとんどあれです。
栗原:座席がちょうど真中だったので、人の足を何度も踏んでしまったのですが、非常に不便ですね。あれは日本の方がいいですよ。ただ、踏まれた人がニコニコ笑って許してくれる。そのへんのマナーというか、同じステージを楽しむのだから、この程度の犠牲はやむを得ないというか、楽しむことに対する連帯感みたいなものを感じました。
──外国の劇場では、お客さんの雰囲気が和やかですよね。
