教本#3
オペラの音響デザイン
小野 隆浩
(びわ湖ホール)
第1項 はじめに
『オペラは、本来「生」で上演できるように作られている。故に「音響」という職分は存在しない』
これは未だに耳にする言葉です。たしかに、表面的にはそう感じられることでしょう。今、上演されているオペラの多くが作られた時代には、確かに職分としての「音響」はありませんでした。しかし、指揮者を始めとして、音楽スタッフが音響的な効果を工夫していたことでしょう。また、その時代には、まだ電気というものが無かったため、電気音響という概念が無かったのだと思います。もし、モーツアルトやベルディが現代に生きていたら、きっと電気音響を用いたのではないかと想像できます。現在、オペラに音響という職分があるというのは、オペラの上演に「音響」が欠かせないものになってきたからなのです。
さて、オペラには3つの時代があるとされています。
歌手の時代、指揮者の時代、そして今は演出家の時代です。
かつては、簡易な吊り物程度の舞台装置を使い、歌手が自分で考えて好きなように演技していた時代があり、次に指揮者がもてはやされた時代を経て、現代のように緻密な演出のもと大掛かりな舞台装置や美しい照明を取り入れて、それに音楽が相まって、素晴らしい感動を観客に与えることができるようになりました。
しかし、このような現在のオペラ公演が、常に完璧な音響空間で行われているわけではありません。実際の舞台では、舞台装置の影響や演出上の制約などで、音響環境に影響を及ぼすことが多くあります。その際に「生音」にこだわり過ぎて不自然、不満足な音になるよりは、あくまでも自然に聞こえるようにする目的で、さまざまな音響手段を用いたほうが観客により高い感動を与えられるのではないのでしょうか。
そのため、オペラの世界にも「見えてはいけない(観客に感じさせてはいけない)けれども、たしかに存在する」私たち音響家が必要なのです。
第2項 プランニング
1) 全ては譜面の中に
「ベルディはラジオ、プッチーニは映画」とよくいわれます。
これはベルディの作品には読み手が自由に想像できる余地がありますが、プッチーニの譜面には全てが書かれているという意味です。プッチーニに限らず作曲家が書き残した譜面には、音符だけでなく、実にさまざまなことが書いてあります。
オペラの音響を手がける場合、最初にすべきことは、オペラ作品の台本でもある譜面を読むことです。
また、読み込むことで音響的に注意が必要な部分が解ります。当然、注釈として譜面に書かれている指示事項(カゲ歌、カゲコーラス、バンダ、効果音)もチェックできます。
音響デザインをするときの基本は、作品を良く理解していることです。
2) 稽古場にて
立ち稽古では、さまざまなことが解ってきます。
稽古を見て懸念される個所の全てに、電気音響でも対応できるように準備します。また、そのことを「生音で大丈夫かと思いますが、一応、機材を準備しておきますので・・・」と音楽スタッフに伝えます。
初めから電気音響ありきというのではなく、必ずこのようにぼかした形で伝え、音楽家に失礼にならない言葉で伝えます。
また、袖中などで演奏される「カゲ演奏」は一次音源(実音)が聞こえてくることを想定し、演出や音楽スタッフと演奏場所や音の方向性(音像)を確認し合います。特に演奏場所に関しては、稽古場であらかじめ方針を相談した後、実際の現場で生音と電気音響のどちらでも可能なように舞台装置や転換などを考えながら、注意深く舞台監督と相談して決めます。
3) 舞台装置を味方に
舞台装置の中でも特に幕類は、音響家にとって敵でもあり味方でもあります。
従来から日本で劇場の幕として使用されている「貫八別珍(かんぱちべっちん)」と最近、多く使用されている「ウールサージ」では音響特性が違います。「英国紗(えいこくしゃ)」と「亀甲紗(きっこうしゃ)」も大きな違いがあります。幕類以外にも様々な舞台装置で使われる素材や加工の音響特性を知っておくことも、音響デザインには必要です。
また、最近では新たな要素も加わってきました。私が仕事を始めた頃は、クラシック音楽にとって、吸音するということは最大のタブーとされていました。そのため全ての音は、反射もしくは吸音しないようにと長い間、考えられていましたが、舞台上の音が全て客席に聞こえる(音響性能の良い)劇場が数多く建設されてくると、音響デザインとして適度な吸音も必要になります。
舞台上の音には、音楽を伝えるにあたって必要なものもあれば、不必要なものもあるからです。
足音や作業音、大型舞台特有の長い残響時間などです。そのため舞台装置や演出の邪魔をしない範囲で、その音楽や作品に合った響きにするため、幕類などで調整し、舞台袖(袖中)での演奏は反射板と吸音板でさらに細かく残響を調整します。反射板といっても巨大な物ではありません。よく使うのは2×4のパネル建材ですが、無ければ劇場にある平台などで代用します。吸音板も特殊なものではなく、入手しやすい建材のグラスウールボードを使います。このように音環境を良くすることで、演奏者のストレスも少なくなります。さらに、このように遮蔽することで、高音圧の効果音やエフェクトSRなどで、演奏者に与える音圧による負担を軽減できます。
第3項 実際のSR、基本編
以下の項目は、通常のオペラ上演で必ず行われる基本的なことです。
1) かなめはモニタースピーカ
オペラでは、オーケストラの演奏音を舞台上にFBします。
この場合の音量は、必要最小限にして、聞こえにくい場所にはスピーカの台数を増やすことで対応します。舞台上の全ての場所で音響的に不自然な場所が無いことが作品を成功させるための秘訣で、音量を上げることによってデッドポイントを無くするという方法では観客席まで聞こえてしまうことがあるので、悪影響が出てしまいます。
2)オーケストラピットのマイクは?
オーケストラピットでのマイクセッティングは、デザイナーによって異なりますが、マルチマイクでセットする人やワンポイントマイク的な手法をとる人もいます。
私の場合は、基本セットとして4本のBLMマイクを【写真1】のようにピットフェンス(客席との手摺部分)にセットしています。BLMということで歌手の声のカブリが気になると思いますが、そのカブリを含めた全体の空間音を収音し、舞台上とオーケストラピットの空間を音響的に同一にすることが私のデザインの基本なのです。
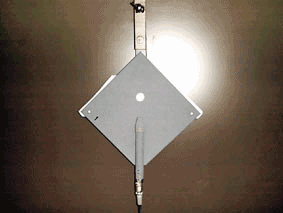
【写真1】ピットフェンスに取り付けたBLM
3)その出し方は?
良く聞こえるようにするといっても、オーケストラピットからの距離感を無視すると舞台上での聞こえ方が不自然になり、いかにも電気音響でモニタースピーカを鳴らしている印象になってしまいます。
本来、オーケストラピットに近い舞台前と、遠い舞台奥ではオーケストラの聞こえ方は違うはずです。このようなとき、私たちは自然な音環境にするために、一次音源に合わせてディレイを掛ける方法をすぐに考えてしまいます。
しかし、舞台奥で演奏するときの演奏者は、自分の声がある程度のタイムラグを伴って客席に聞こえることを予測して指揮に合わせていますので、この方法を使うのは非常に危険です。
そのためには、距離による時間差を利用するのではなく、音質を調整して音のニュアンスを変えます。良く使う方法は、舞台前ではオーケストラピットの弦楽器が良く聞こえてきますので、その他の楽器を多少強めに出し、舞台奥では逆に弦楽器をほんの少し強めにしてトータルで距離による高域減衰を考えて少しだけ丸い柔らかい音にします。オーケストラピットからの距離を考えると、舞台前に対して舞台奥の音量を下げたくなりますが、実際には舞台前ではオーケストラピットからの生音が聞こえてきますので、結局スピーカから出ている音は同じぐらいの音量になります。
このように音量的には同じように出ていても、あくまでもオーケストラピットから自然にオーケストラが聞こえてくるような印象の音が望ましいわけです。
この基本がきちんと作られた上で、楽曲によってエキストラマイク【写真2・3】を使用し、舞台上を声楽家が歌いやすい状態にします。
例を挙げるとモーツアルトの作品では木管系、ヴェルディの作品ではハープといったように演奏者がガイドをとりやすい楽器を全体のバランスを考慮しながら足していますし、楽曲によってはコントラバスという極端なケースもあります。

【写真2】譜面台に取り付けることで、マイクは常に楽器の側にある

【写真3】この金具を使ってピットフェンスにマイクを装着
この楽器をどうやって判断するかは、CDを聞きながら自分で歌ってみると必要な楽器が解ります。そして絶対に忘れてはならないことですが、オペラの場合では舞台上に聞こえるオーケストラはあくまでも伴奏音楽です。
楽曲を良く聞かせようとメロディラインを強調し、すばらしいバランスでシンフォニー的に作り上げるのも結構ですが、そのあげく声楽家が歌いにくくなったのではモニターの意味がありません。声楽家と常にコミュニケーションをとり、問題が無いかを確認します。
また、クラシック音楽の演奏家の多くは、電気音響に対して非常に敏感です。そのため、歌っていてモニタースピーカの音が気にならないこと(気付かないような音環境)が大切です。つまりオーケストラの音そのものを意識せず、自然にオーケストラに包まれたような音環境が演奏家にとって最良の状態なのです。
さらに、この状態をきちんと作り上げれば、演奏音が客席にも十分に伝わるため、SRする必要はほとんどありません。もし、どうしてもSRする場合でも、ほんの少しにして音質やニュアンスを変えることで対応できますので、自然に聞こえる音環境を保つことができます。違和感がある場合は、さまざまな種類の音がありすぎてダンゴ状態(音圧の喧嘩)になっているときです。また、舞台袖の副指揮者や各技術セクションのオペレートブースのモニタリング環境も同様に作っていきます。
作品はみんなで作っているのですから、モニターが必要なスタッフには何の音が必要なのかを聞いて、モニター音を丁寧に調整します。このように様々な方法で全体の音を整理することで、演奏家が演奏しやすく、スタッフも動きやすい音環境が整い、数多くの人間の息がぴったりと合って、素晴らしい舞台作品が生み出されるのです。
4 )SEについて
レチタティーボ(オペラ特有の歌うような会話)でのSEは問題がないのですが、楽曲の中のSEは必ずピッチを合わせます。これは楽曲と馴染むようにするためで、できるだけ楽曲の基音との間で和音を構成するように作ります。なお低域成分が多いSEは、多少高めのピッチにしておかないと楽曲に埋もれてしまうことがあります。
5)カゲ歌のSR
音楽上、異なる場所からの声として扱われるカゲ歌ですが、歌う場所を決めても、その位置では舞台装置の影響で全く聞こえない場合があります。そのときのSRは、あくまでもカゲ歌ですからONで聞こえないようにすることが大切です。そのため、スピーカを舞台奥の方向に背けるなどして対処します。
6)カゲコーラスやバンダのSR
カゲコーラスやバンダ(ピット以外のオーケストラ)は、特殊な演出を除き、音楽家や演出家が意図する方向(位置)から聞こえるようにするため、その場所で演奏します。
上手から聞こえたい場合には上手で演奏するのです。しかし、期待した効果が得られない場合はSRすることになります。マイクセッティングは演奏規模により異なりますが、必ず複数のスピーカから出力させ、自然なズレや舞台装置の乱反射を利用して電気音響を感じさせないようにします。
カゲの演奏の聞こえ方として点音源はあり得ないからです。カゲ歌やカゲコーラス、バンダのマイクは、音響調整室に立ち上げずに小型のパワードシステムを使い、そこでミキシングしてSRすることがよくあります。
第4項 実際のSR、特殊編
前述したように舞台上の音環境を整理することによって、ほとんどのオペラの上演に適した音環境が作れます。
しかし、劇場固有の音響性能や演奏の問題により、舞台上の声(歌唱)をSRする特殊な場合があります。
1)音源点を大切に
視覚と聴覚の一致が全てです。SRする場合も、あくまでもその演奏者から音が聞こえて来なければ自然に聞こえません。また音量は、肉声をマスキングするほど大きくしませんので、ある程度は音源からの直接音が聞こえています。そのため、音原点である歌い手(一次音源)の声と、SR音(二次音源)の時間軸を合わせる必要があります。
その方法は、次の2つがあります。
- 方法1:一次音源の近くにSR用スピーカを置く。単純ですが効果は絶大です。
- 方法2:ディレイを使用し、一次音源と二次音源の時間差を補整します。この合わせ方はパルス音源を使用する方法が一般的に行われています。パルス音源が無い場合はメトロノームでも簡単に合わせられます。
以上のどちらかの方法で時間軸を合わせますが、方法2の場合には条件があります。歌をクリアーに集音するためピンワイヤレスを使ってということを考えがちですが、実際には歌手の動きによって生じる音原点の移動に対して、常にディレイタイムを追従するわけにはいきません。音源をマスキングするほどの音量でSRしている場合は音源の直接音が聞こえないため時間軸のズレは気にならないのですが、一次音源が聞こえている場合は二次音源が早く聞こえると不自然です。
そのため、私はマイクが音原点と共に移動してしまうピンワイヤレスは使いません。クリアーな集音よりも自然に感じられる音場を重要視するため、固定位置で1本ずつディレイ調整をした数本・数列のマイク間(マイク群)を使います。そのマイク間を音原点である歌い手が移動して行くに従って音像も同様に移動していくという方法を用います。当然、マイクに遠い音は遠く、近い音はリアルになりますが、結果として自然に聞こえます。
2)EQは大胆に(フラットEQに固執しない)
ディレイで調整されたマイクを、さらにEQで大胆に加工します。
何度も言いますが、私の場合はある程度、直接音が聞こえている上でのSR手法ですから、音源で足りない成分を補足していると考えてください。そのため、明瞭度を上げるために、極端に子音域だけをSRすることもあります。大胆な加工かも知れませんが、あくまでも一時音源とSR音が混じったときに自然に聞こえるようにEQの調整を行います。
3)マイクセッティングに対する固定観念を捨てる
使うマイクはやはり見栄えの点からバウンダリーマイクを多用し、可能であれば【写真4】のような「マイクけこみ」を使用します。
それ以外に数列のマイク群を作るため【写真5】のように舞台装置に組み込んだり、小道具類にワイヤレスピンなどを仕込んだりすることもあります。使用する状況で様々なセッテイングを行いますが、一般的なマイクスタンドを使うことはほとんどありません。観客にも、そして演奏家にも、聴覚的には当然のことですが、視覚的にもマイクの存在を意識させないことが大切です。

【写真4】PCC160の前にある板はマイク隠し

【写真5】マイクホルダー中の変換ネジを舞台装置に直接ネジ止め
第5項 最後に
楽曲や舞台作品も、それぞれの固有のアトモスフェア(空間に満ちているもの)を持っています。そのアトモスフェアと一緒の印象の音であればどんな音も作品にとって必要な音であり、逆にすばらしい音であっても楽曲や舞台作品のアトモスフェアと大きく掛け離れた印象を与えてしまう場合は作品にとって不必要な音だと思います。
生音がいつでも自然に聞こえ、SRしているから必ず不自然に聞こえるとは限りません。生音にこだわりすぎて楽曲や作品空間の印象が不自然に変わるよりは、様々な方法、手段を用いて楽曲にとって自然な空間や空気感を感じられる方が良いのではないかと思います。
